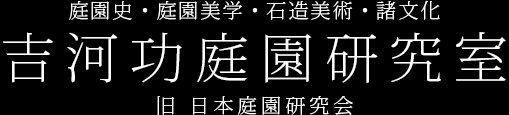吉河整備指導庭園
2024/07/26冨賀寺庭園(愛知県新城市)修復なる
冨賀寺は、宇利峠を挟んで東の遠州地方と関係の深い真言宗の古刹で、静岡県側の摩訶耶寺(浜松市)とも縁が深く、江戸初期の名園 (新城市指定名勝)が保存されています。
その本格的な整備作業は、2010年に庭研によって行われました。その時、それまでは枯滝と思われていた滝石組が、上方にある「弁天池」から引水した生得の滝であることが明らかとなり、落水の景が復原されました。その後ザリガニの異常繁殖等によって、滝石組や池泉護岸石組の裏に漏水が生じ、土が流れ出す事態になった為、2024年2月初旬までに、不透水性粘土を用いて補修作業を行い、同時に護岸杭の打ち直しも行いました。現在は、本庭の特色である多数の築山にタマリュウがよく繁茂し、特色ある池泉庭園の美景が際立ってまいりました。ここに修復後の、三点の写真を紹介致します。

修復後の全景

築山と滝石組を望む
2022/01/05摩訶耶寺庭園(浜松市)の整備修復終わる
摩訶耶寺庭園(鎌倉前期作庭)は、数ある古庭園の中でも、その石組美と、全庭の空間構成において、最も傑出した名園の一つです。
1968年6月に荒れ果てた本庭が発見され、慎重な整備を行って世に出したのですが、当初の造形を尊重し、意図的な改修は一切行っておりません。その石組には平安時代の『作庭記』に記載されている石組造形がよく残されております。
伊勢神宮の神領であった当地の特色が、このような名園を生み出したことは間違いありません。
しかし、近年の気候変動による豪雨や、地下水の池への流入が顕著になってきたのが原因で、石組の一部に変動が見られるようになりました。
このたび静岡県と摩訶耶寺から修復要請があり、本年4月から6月にかけてその整備作業が行われ、特色ある石組も無事復原されました。
発見当初から、毎年のように撮影を続けてきた吉河会長による細部写真を参考とし、慎重な作業が進められましたので、驚くような古庭園の美景が再現されました。
『庭研』421号(2021年秋号)を「摩訶耶寺庭園修復特集号」(限定150部)として発行致しましたので、詳しくはそちらをお読み頂ければ嬉しく思います。
2020/09/04旧円融寺庭園の紹介
今回は庭研が世に出した古庭園の内、その最も早い実例である長崎県大村市「旧円融寺庭園」を紹介します。本庭は1 9 6 9 年3 月庭研の調査によって、江戸初期名園であることが判明しましたが、それまでは全体がツツジに覆われ庭園造形は不明の状態でした。1 9 7 6 年に国の名勝に指定されたことにより、1 9 7 9 年1 0 月2 3 日~ 3 1 日、吉河会長の指導によって「旧円融寺庭園保存修理事業」が行われ、名園が姿を現しました。
小高い丘上にあり、徳川家代々の位牌を安置するために建立された「円融寺」の後庭として築造された歴史があります。
幅5 0 m にも及ぶ山畔に青石を主体とした4 0 0 石近い石を組み込んだ築山式枯山水庭園です。全国的にも希な造形を持つ庭園として、庭園史上貴重な存在となっております。
なお一部の書籍に本庭を「江戸末期作庭」としているものがあるようです。
誤説にご注意下さい。本年の『庭研』4 1 6 号に吉河会長の詳しい記載があります。参照をお勧めします。

旧円融寺庭園中央部の美景
2016/03/19妙経寺庭園整備報告
大分県杵築市にある妙経寺庭園は、庫裡書院の北側にある約188坪の築山式枯山水庭園であり、江戸中期に作られた名園です。
築山石組、枯滝石組、切石橋、 陰陽石、岩島等の造形はまことにユニークなもので、それに露地の要素も取り入れ、枯池に雪見燈籠を配して景をとるなど、優れた景観が見られます。
特筆すべ きことは、切石橋にある銘文によって、施主、作庭年月、作者のすべてが明らかになっていることで、このような庭園は日本庭園中でも珍しく、歴史的にも貴重な史料となっております。
本庭は2001年に庭研による整備が完了し、2003年2月には『妙経寺庭園整備調査報告書』が発行され、3月には早くも大分県指定名勝になりました。

妙経寺庭園中央部を望む(書院からの眺め)

妙経寺庭園枯池の景観
2016/03/19靖國神社庭園整備報告
靖國神社(東京都千代田区九段)の本殿西北部にある日本庭園は明治時代に作られた名園です。
長らく荒廃していましたが、1999年に庭研技術部会の手で 整備が行われ、粘土による古式工法等を用いて池を修理しました。
その結果都内でも最も見事な庭園として蘇ったものです。
特に当初のままの造形を見せる滝石組の豪華さは特筆されます。また花崗岩の切石橋は6.27mもあり直橋としては日本最大のものです。

靖國神社庭園池泉中央部

靖國神社滝石組
2016/03/19海蔵寺庭園整備報告
広島市西区田方にある海蔵寺は、室町時代に創立された曹洞宗寺院ですが、江戸初期に現在の地に移されました。その時、建物と同時に作庭されたのが本庭です。当地の石材である平天の花崗岩を多用した興味深い石組が保存されており、原爆の被害をまぬがれた古庭園としてまことに貴重なものです。庭研が1998年に整備調査を行い、その報告書も発行されています。またこの報告書によって、正しい寺史が解明されました。
2016/03/19阿波国分寺庭園整備報告
阿波国分寺庭園(徳島市)は、当地独特の青石と、その板石を駆使した豪快な石組が特色で、桃山時代を代表する古庭園として2000年に国の名勝に指定されました。
庭園の中に、江戸末期になって薬師堂(本堂)が建てられましたので、庭が分断されている感がありますが、鋭さのある多数の巨石石組は、日本庭園の素晴らしい造形力をよく示しています。
庭研が1993年に整備した庭園であり、その調査報告書も発行されています。
なお近年、本庭を江戸末期作庭とする新説も出されておりますが、寺の経済状態を無視した説であり、とても認められません。

国分寺庭園全景

国分寺庭園築山石組